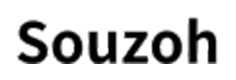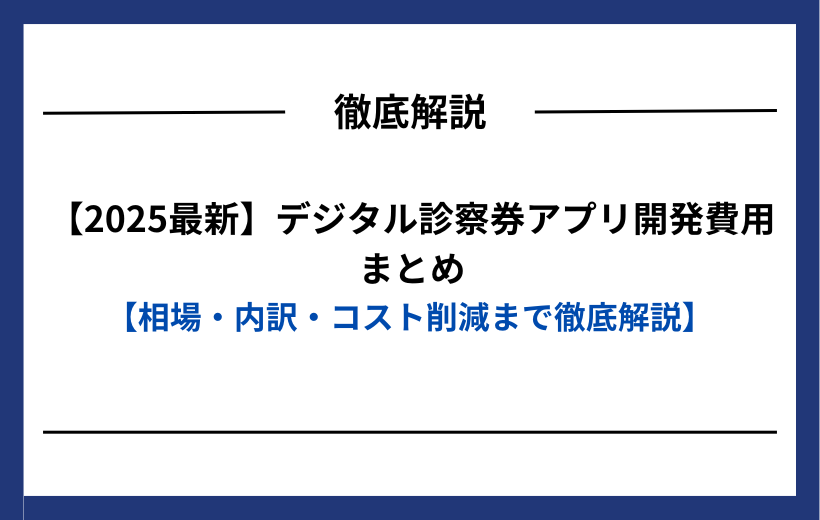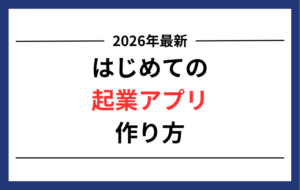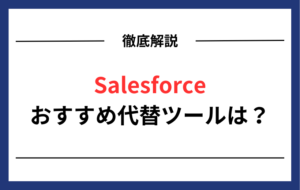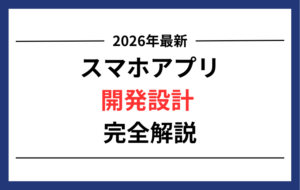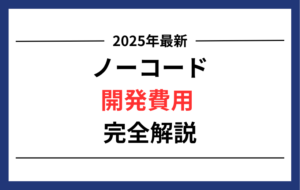はじめに
✅ ノーコードでデジタル診察券アプリを作りたい方
✅ クリニック向けアプリを低コスト・短期間でリリースしたい方
✅ デジタル診察券アプリの必要機能・費用感・開発手法を知りたい方
本記事では、ノーコードを活用してデジタル診察券アプリを開発するための具体的なステップから、必要機能・開発費・ツールの選び方・成功事例までをわかりやすく解説しています!
- 『一律50万円』にてご要望のアプリ/システムの土台開発!
1. 結論|ノーコードでも開発費は100〜600万円規模。ただしコスト削減ポイントは明確にある
「ノーコードならもっと安く作れると思ってた…」という声は多くありますが、実際には委託開発だと数百万円規模になるケースがほとんどです。
なぜなら、デジタル診察券アプリでは以下のような業務連携性・信頼性が高い機能が求められるからです。
- 患者情報の管理・電子カルテ連携
- 予約受付(オンライン受付・QRコード発行)
- 来院確認(受付画面でのチェックイン)
- 診察券の定期更新・プッシュ通知 など
とはいえ、安心してください。コスト削減の余地は十分にあります。
- MVPを意識した段階的開発
- 汎用ノーコードツールの活用
- 不要な外注を避ける運用設計
これらの工夫で、初期コストとランニング費用を大きく圧縮できます。
以下では、費用相場の具体的な内訳を見ていきましょう。
まずは無料相談
\ 30秒でお問い合わせ! /
2. デジタル診察券アプリの開発費用相場(手法別・規模別)
デジタル診察券アプリの開発費用は、開発手法(ノーコード or フルスクラッチ)と、アプリの規模・機能の複雑さによって大きく変動します。
ここでは、よくあるパターンごとに相場の傾向を解説します。
2-1. フルスクラッチ開発の相場感
すべてをコードベースで構築するスクラッチ開発は、自由度が高く、業務やUXにあわせた細やかな設計が可能です。しかしその分、開発工数・費用も大きくなりがちです。
- 最低限の機能のみ(患者情報管理、簡易予約フォーム、管理画面など):200〜450万円
- 標準的な構成(予約受付・QR発行、来院通知、患者管理、電子カルテ連携など):450〜1,250万円
- フルカスタム構成(複数診療科対応、医師別アカウント管理、診療データ分析機能、外部システム連携など):1,250万円〜2,000万円以上
たとえば、複雑な保険診療ルールや業界特有の診療フロー(例:専門学会向け診療連携など)に対応する必要がある場合は、スクラッチ開発が有効です。
とはいえ、すべてをスクラッチで作る必要はありません。まずはノーコードで検証し、スケール段階で必要な部分のみカスタムするという方法が、費用対効果の面でも現実的です。
2-2. 機能別・ツール別の開発費用比較
必要な機能だけを絞り、段階的に投資を増やすことでリスクを抑制しつつスピーディに価値検証するのがコスト最適化の要諦です。以下は国内ユーザー向けに、Click/Bubble/Adalo の各ノーコードツールを用いた開発費用の目安です。
| アプリ規模 | Click 開発費用目安 | Bubble 開発費用目安 | Adalo 開発費用目安 |
|---|---|---|---|
| 最小構成(MVP) | 50万~150万円 | 100万~250万円 | 50万~150万円 |
| 中規模(基本機能) | 150万~300万円 | 150万~300万円 | 150万~300万円 |
| 大規模(高度機能) | 300万~650万円 | 300万~650万円 | 300万~650万円 |
- 最小構成(MVP)例
- Click:テンプレート+患者登録+簡易予約リスト中心で低コスト
- Bubble:予約フォーム連携+カレンダー連動+プッシュ通知最小限
- Adalo:QR発行+患者ID認証のみのシンプル構成
- 中規模(基本機能)例
- 会員(患者)管理・予約リマインド・診療科別チャット機能など標準的コミュニティ機能
- Click/Bubble/Adalo いずれも同等の工数想定
- 大規模(高度機能)例
- 診療データBIダッシュボード、複雑な自動化フロー、外部システム(電子カルテ・レセプト)連携などを追加
- データ容量増加と患者数増大により工数が跳ね上がる
「まず MVP を上記レンジの低価格帯でローンチし、運用データやユーザー要望を踏まえて中規模→大規模へ段階的に拡張する」ことで、不要な投資を避けつつスピード重視の開発体制を実現できます。
3. ノーコード開発に潜む「見えないコスト」も押さえておこう
ノーコード開発は、初期の開発費用を抑えられる点が大きな魅力です。とはいえ「開発して終わり」ではありません。アプリをリリースし、運用し続けていく中では、じわじわ効いてくる“見えないコスト”が存在します。
特に注意したいのは、以下の3つのポイントです。
3-1. プラットフォーム利用料・連携ツールの費用
ノーコードでよく使われる開発プラットフォーム(例:Adalo、Bubble、Clickなど)は、無料プランもありますが、商用利用や機能制限を解除するには有料プラン(月額4,000〜10,000円前後)が一般的です。
また、デジタル診察券アプリでは「SMS予約リマインド」「電子カルテ連携」「オンライン決済」「ドキュメント共有(保険証など)」といった外部サービス連携が必須になるケースが場合も多く、ZapierやMake、Firebase、Brevoなどの外部ツールを使う場合もあります。これらの連携ツールには使用量に応じて月数千円〜1万円前後の費用がかかるため、あらかじめ見積もっておくことが大切です。
3-2. ストレージ・ドメインなどのインフラコスト
患者の保険証や紹介状、検査結果PDFなど機密性の高いファイルをアップロード・ダウンロードする機能がある場合は、厳重なストレージ管理が求められます。ノーコードツールに含まれている場合もありますが、容量が増えると追加課金が発生することがあります。
また、クリニック公式ドメインで運用する場合は、独自ドメイン取得やSSL対応、DNS設定のほかに「プライバシーポリシー」のページ設置や「法的要件」に合わせたサーバホスティングが必要です。これらのインフラ系コストは、年間で1万〜5万円前後を目安にしておくと安心です。
3-3. 保守・運用のランニングコスト
アプリを公開した後にも、医療情報の取り扱いにおけるセキュリティパッチの適用や電子カルテ連携部分のアップデート対応、患者からの問い合わせ(予約変更・診察時間の問い合わせなど)対応などが発生します。これを外部の開発者やITベンダーに依頼する場合、月1〜5万円前後の保守費用がかかることが一般的です。
特に医療系アプリでは、法規制やセキュリティ基準の変更に素早く対応しなければならないため、改善フェーズとしてある程度の予算を確保しておくと安心です。初年度は、開発費とは別に保守運用費も含めて検討するのが現実的です。この辺りの予算感は、アプリの規模や内容に大きく左右されます。
まずは無料相談
\ 30秒でお問い合わせ! /
4. 開発費以外にかかる代表的な3つの費用
アプリの開発は、あくまでスタートラインです。実際にビジネスとして成立させるためには、「運用」「改善」「集客」「公開」といった、開発後の“運営フェーズ”が欠かせません。
ここでは、見落とされがちだけれども重要な4つの費用項目を紹介します。これらを事前に把握しておくことで、より現実的な予算設計が可能になります。
4-1. 不具合対応・ユーザーフィードバック対応
アプリを公開すれば、クリニック・患者双方からリアルな声(エラー報告や使い勝手の指摘、予約機能に関する改良要望など)が届きます。
例えば、「予約画面が反応しない」「QRコードが読み取れない」といった不具合や、「診察前にアンケートを取りたい」「診察後にフォローアップメッセージを送りたい」といった機能改善要望が出るかもしれません。
こうした声に応え、スピーディに改善へつなげるには、継続的な開発体制と柔軟な改修予算を確保することが必要です。特にリリース直後はクリニック側のオペレーションに直結するため、迅速な対応が信頼獲得につながります。
4-2. マーケティング・プロモーション費用
どんなに優れたデジタル診察券アプリを開発しても、クリニック側や患者側に認知されなければ使われません。特に地域密着型クリニックや専門クリニックの場合は、以下のようなマーケティング施策が重要です。
たとえば…
- SNSを使った地域向け広告やクリニック紹介動画の配信
- Webサイト・LP制作+SEO対策
- クリニック公式Webサイト・ランディングページ制作+SEO対策
- 病院情報サイトや口コミサイトへの掲載、(医療系プラットフォームへの掲載費用)画
など。重要なのは「費用をかけてどの患者層を獲得するのか」という視点です。KPI(例:新規患者数、リピート率、予約経路ごとのコンバージョン率)を定め、施策ごとの効果を検証しながら、段階的に改善を図ることが、費用対効果を最大化するコツです。
4-3. ストアリリース費用(iOS/Android)
アプリを公開するには、iOS/Android各ストアへの登録が必要です。これは1回限りまたは年間で発生する費用で、それ自体は大きな負担ではありませんが、アプリ内課金を導入する場合の手数料が、ビジネスモデルに大きく影響してきます。しかし、保険証情報の取り扱い・診療報酬請求システムと連携する場合にアプリ内課金や手数料が発生するケースがあります。
| プラットフォーム | 登録料 | アプリ内課金の手数料 |
|---|---|---|
| App Store(iOS) | 年間99ドル(約15,000円) | 課金額の15〜30% |
| Google Play(Android) | 初回25ドル(約3,750円) | 課金額の15〜30% |
たとえば、保険証登録やオンライン決済機能をアプリ内に組み込む場合は、決済手数料を差し引いたうえで診察料や検査料収支が成立するかを事前にシミュレーションしておくことが重要です。
このように、アプリ開発には「作るための費用」だけでなく、「運用して育てていくための費用」が必ず発生します。
リリースがゴールではなく、そこからが本番。運用・改善・集客・収益化までを見据えた、事業全体の設計こそが、本当に必要な“予算設計”と言えるでしょう。
5. 開発費に差が出る5つの要素
アプリの開発費用は「機能数×開発期間×人件費」で決まる…と単純に思われがちですが、実際にはもっと複雑です。
同じ“デジタル診察券アプリ”に見えても、見積もりに大きな差が出るのは、以下のような構造的な違いが影響しているからです。
5-1. 機能の数と構成
最もわかりやすいのが、「搭載する機能の数と構成の複雑さ」です。
- 単一科・予約管理のみ(診察日時リスト+予約フォーム)
- 複数科対応 × カレンダー連携 × 保険証登録 × 医師プロフィール表示 × 診察後フォローアップ通知…
といった形で、機能が増えるほど設計・実装・テストの工数は一気に膨らみます。
さらに、ユーザー数の増加に耐える設計(スケーラビリティ)を前提とするかどうかも、開発負荷に大きく影響します。
5-2. チケット・決済・入場処理などの業務ロジック
診療系アプリに特有なのが、診察料金プラン・支払い・保険証発行・来院チェックインといったリアルな業務と直結したロジックの存在です。
- 診察料金プラン(保険診療・自費診療の違い、各種オプション)
- QRコード/バーコードの発行とスキャンによる受付管理
- オンライン決済(クレジットカード・電子マネー)との連携
- 診察枠ごとの予約上限・当日キャンセル対応
これらをリアルタイムで正確に処理する仕組みをどこまで細かく作るかによって、必要な設計力・開発工数は大きく変動します。
5-3. セキュリティ・法令対応レベル
患者情報、特に保険証情報、診察履歴を扱う場合は、セキュリティ設計・法令対応の水準が費用に関係してきます。。
- 通信の暗号化(TLS/SSL)
- 二段階認証・OAuthなどの安全なログイン認証(医師/スタッフ用・患者用の権限分離)
- 電子カルテ連携およびPHR(Personal Health Record)連携のセキュリティ要件
- 個人情報保護法(PIPA)や医療情報ガイドラインへの準拠、プライバシーポリシーの整備
また、診療内容や処方箋発行機能を追加する場合は、さらに高いレベルの要件(厚労省のガイドライン)を満たす必要があります。ノーコードではこうした細かな要件を自前で対応できない場合もあるので、開発以前の計画の段階で把握しておく必要がありますが、おおむねプラットフォーム側が提供している機能でカバー可能なケースもあります。
5-4. デザイン・UI/UX の精度
「初めて使う患者でも直感的に操作できる」ことは、診察券アプリにとって非常に重要です。利用頻度が高くないユーザーでもスムーズに使えるUI/UXでなければ、離脱リスクが高くなるからです。
- 診察予約画面の操作導線(予約日時の選択、医師選択、病状入力フォームなど)
- スマホ画面での視認性(高齢患者でも見やすいフォントサイズ、アイコン配置)
- 予約リマインダーや休診日通知のタイミング・文言
- オンライン問診フォームや診察結果表示のUI設計
など、クリニックの診療フローに合わせて最適化したい場合は専用UI設計に工数がかかりますが、テンプレートを活用してコストを抑えることもできます。
5-5. 要件定義の明確さと仕様変更の頻度
見積もりより費用が膨らむ最大の要因は、開発中の仕様変更です。
- 「やっぱり初診患者用アンケートも表示したい
- 「診察後フォローアップ機能を追加したい」
- 「保険証の登録方法を変更したい」
…といった追加要望があるたびに、設計・実装・テストが繰り返され、開発期間も費用も膨れ上がります。
そのため、最初の段階で「必須機能」と「後で考える機能」の線引きを明確にしておくことが、結果的に開発費用を抑える最大のコツです。
6. 費用を抑えるための賢いアプローチ3選
ここまで読んで、「結局アプリ開発って高い…」と感じた方も多いはず。でも、費用をかけるべきポイント・削れるポイントの見極めさえできれば、コストパフォーマンスの良い開発は十分可能です。
ここでは、実際に多くの成功事例が取り入れている“賢いコスト削減法”を5つ紹介します。
6-1. MVP思考で「段階的に機能追加」する
最初からフル機能を詰め込もうとすると、費用もスケジュールも跳ね上がります。
まずは最小限の機能でリリースし、ユーザーの反応を見ながら機能を優先度順に追加していくことで、無駄な工数・予算を削減できます。
6-2. 実績のある開発会社に依頼する
アプリ開発における“安さ”は、かえって高くつくことがあります。経験の浅い開発会社やフリーランスに頼むと、後からの手戻りやセキュリティ漏れが多発するケースも。
特に医療システムや診察フローに精通した開発会社なら、設計段階から余計なコストや法令対応漏れを回避できます。
6-3. 補助金・助成金制度を活用する
IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金など、公的な支援制度を活用すれば、自己負担額を数十%〜最大80%程度まで削減できる可能性があります。
ノーコード開発や業務改善系のアプリは、補助対象として採択されやすいため、早い段階で申請準備を進めるのが◎。
7. まとめ|「つくる」より「育てる」視点で設計する
アプリ開発とは、単なる「ものづくり」ではなく、「事業づくり」です。どれだけ良い機能を備えていても、それが使われ続け、収益を生み、チームが持続的に運用できなければ意味がありません。
ノーコードの活用や補助金制度の併用によって、たしかに初期コストは抑えられます。しかし、それ以上に大切なのは、アプリが「使われ続ける構造」を持っているかどうかです。
そのためには、開発フェーズの前にこそ考えるべき問いがあります。
- 誰に、何を届けるのか?
- どう収益を生み、どう成長させていくのか?
- どのくらいの体制・コストで運用を回せるか?
こうした問いをもとに、MVP設計・ロードマップ策定・体制設計まで含めた「全体像の構想」が必要です。
最小の投資で最大の成果を出すためには、「作る技術」以上に「育てる視点」と「戦略設計力」が武器になります。
その準備こそが、あなたのアプリを“単なるプロダクト”から“持続可能な事業”へと進化させる土台になるのです。
一律50万円構築サービス_6パックはこちら!
- 6パックについてもっと詳しく知りたいといった方は
まずは下記から資料をダウンロードください!
- 6パックでどこまでのアプリが作れるのか相談したい
- 実際に6パックでアプリの土台を開発したい など
上記のような方は、下記より無料相談のお申し込みをお願いいたします!
ノーコード開発に関するご相談はソウゾウまで!
ソウゾウでは、数多くのノーコード開発実績より、お客様のプロジェクトの目的ごとに最適なノーコードツールのご提案〜設計〜デザイン〜実装〜リリース〜保守運用まで一貫してサポートさせていただいております。
・ノーコードを活用し、アプリ・システムをマルっと構築して欲しい
・アプリ/システムの土台の構築依頼とその後の運用の内製化(開発人材の内製化)までやってほしい
・ノーコード人材/開発人材/IT人材を内製化してほしい など
上記のようなご要望をお持ちの方は、下記よりお気軽にご相談ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
まずは無料相談
\ 30秒でお問い合わせ! /