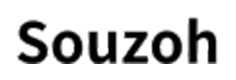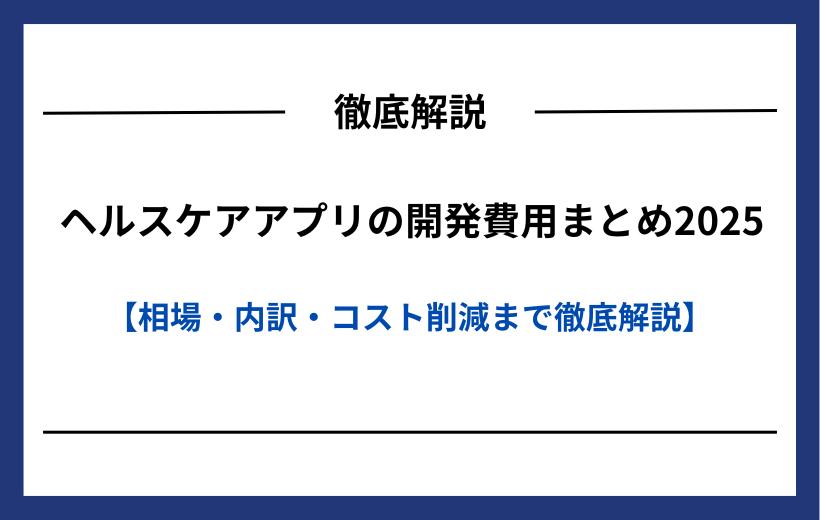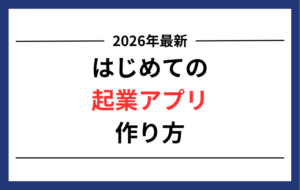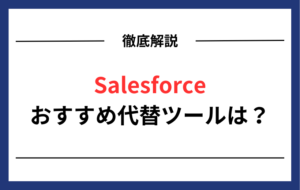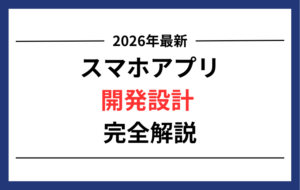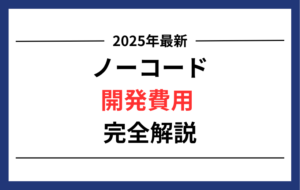| アプリ規模 | ノーコード開発 | フルスクラッチ開発 |
|---|---|---|
| 最小構成(MVP) | 50万〜150万円 | 200万〜450万円 |
| 中規模(基本機能) | 150万〜300万円 | 450万〜1,250万円 |
| 大規模(高度機能) | 300万〜650万円 | 1,250万〜1,950万円〜 |
はじめに
✅ ノーコードでヘルスケアアプリを作りたい方
✅ 開発費用や期間を抑えて、早くリリースしたい方
✅ コミュニティアプリの機能・費用感・開発手法を知りたい方
本記事では、ノーコードを活用してヘルスケアアプリを開発するための具体的なステップから、必要機能・開発費・ツールの選び方までをわかりやすく解説しています!
1. 結論|ノーコードでも開発費は数百万円規模。けれど削減ポイントは明確にある
「ノーコードなら安く作れるって聞いたけど、実際どうなんだろう?」 そう思っている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、ノーコード開発はスクラッチ開発(フルコード)と比べて初期費用を抑えやすく、開発スピードも速いのが魅力です。
しかし、委託開発という形でプロに依頼する場合は、数百万円規模の費用がかかることが一般的です。
とはいえ、安心してください。開発費には明確な「下げどころ」があります。
本記事では、開発費の相場・内訳・よくある見落とし・そして賢いコスト削減術まで、現実に即した情報を“構造的に”まとめました。
これからヘルスケアアプリを立ち上げたい方にとって、企画から運用までの全体像が見える内容となっています。
まずは、気になる開発費の相場から見ていきましょう。
30秒でお問い合わせ!
- どのノーコードツールが最適なのか知りたい
- ノーコード開発の見積もりが欲しい
- Click・Larkについて詳しく知りたい
- ソウゾウのサービスについて知りたい
上記のような方はお気軽にお問い合わせください!
2. ヘルスケアアプリの開発費用相場(手法別・規模別)
ヘルスケアアプリの開発費用は、「どのような開発手法を用いるか(ノーコード or フルスクラッチ)」と、「実装したい機能の量・複雑さ(アプリの規模)」によって大きく変わります。
ここでは、一般的な相場感を、開発手法ごとにわかりやすく整理してご紹介します。
2-1. フルスクラッチ開発の相場感
フルスクラッチ開発は、ゼロからすべてをコードで構築する方法であり、自由度が非常に高い一方で、開発期間と費用は大きくなります。
セキュリティの高度化や、特殊な要件への対応、医療機器との個別連携など、ノーコードでは難しい機能も実装可能です。
下記は、規模別のフルスクラッチ開発費用の一例です。
| 開発規模 | 例 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| MVP(最小限の機能) | ユーザー登録、健康データの記録機能など | 200万〜450万円 |
| 中規模アプリ | 健康管理、生活習慣の可視化、カレンダー連携、食事・運動記録など | 450万〜1,250万円 |
| 大規模・高機能アプリ | AI分析、病院・診療所とのシステム連携、リアルタイム処理、複数端末連携など | 1,250万〜2,000万円以上 |
業界や事業規模によっては、スクラッチでの開発が必要となる場面もありますが、初期段階であればノーコードをうまく活用することで、コストを抑えつつ市場投入することも十分に可能です。
2-2. 機能別・ツール別の開発費用比較
必要な機能だけを絞り、段階的に投資を増やすことでリスクを抑制しつつスピーディに価値検証するのがコスト最適化の要諦です。以下は国内ユーザー向けに、Click/Bubble/Adalo の各ノーコードツールを用いた開発費用の目安です。
| アプリ規模 | Click 開発費用目安 | Bubble 開発費用目安 | Adalo 開発費用目安 |
|---|---|---|---|
| 最小構成(MVP) | 50万~150万円 | 100万~250万円 | 50万~150万円 |
| 中規模(基本機能) | 150万~300万円 | 150万~300万円 | 150万~300万円 |
| 大規模(高度機能) | 300万~650万円 | 300万~650万円 | 300万~650万円 |
- 最小構成(MVP):
- Click:テンプレート+カスタムリスト中心で低コスト
- Bubble:外部API連携やカスタムプラグインを最小限に
- Adalo:ペイメント+認証のみのシンプル構成
- 中規模(基本機能):
- 会員管理・通知・チャットなど標準的なコミュニティ機能を実装
- Click/Bubble/Adalo いずれも同等の工数が想定されます
- 大規模(高度機能):
- BIダッシュボード、複雑な自動化フロー、外部システム連携などを追加
- 高度カスタマイズやデータ容量増加に伴い、工数が跳ね上がります
「まず MVP を上記レンジの低価格帯でローンチし、運用データやユーザー要望を踏まえて中規模→大規模へ段階的に拡張する」ことで、不要な投資を避けつつスピード重視の開発体制を実現できます。
3. ノーコード開発に潜む「見えないコスト」も押さえておこう
ノーコード開発は、初期の開発コストを抑えられる点で非常に魅力的です。しかし、実際のアプリ運用フェーズに入ると、徐々に効いてくる“見えないコスト”も存在します。特にヘルスケアアプリは、データの安全性や信頼性が問われる分野のため、意外な出費が後から発生することも少なくありません。
この章では、ヘルスケアアプリで注意しておきたい3つの「ランニングコストの盲点」について解説します。
3-1. プラットフォーム利用料・連携ツールの費用
ノーコード開発で広く使われているAdalo、Bubble、Clickなどの開発プラットフォームには無料プランもありますが、商用利用をするには有料プラン(月額4,000〜10,000円程度)が基本となります。
ヘルスケアアプリでは特に、ユーザーごとのデータ保持やカスタム設定が必要になるため、有料プランへの加入はほぼ必須と考えた方が良いでしょう。
また、アプリに通知機能や健康デバイスとのデータ連携(例:Fitbit、Apple Health、LINE通知、メール送信)などを追加したい場合は、Zapier、Make、Brevoといった外部自動化ツールの導入が必要です。
これらも従量制の料金体系が多く、月額数千円〜1万円程度のコストが発生します。
【ポイント】
初期開発費に比べれば小さな額でも、長期的に運用すると累積コストになるため、機能設計時点で使用するツールと月額費用をシミュレーションしておくことが大切です。
3-2. ストレージ・ドメインなどのインフラコスト
ヘルスケアアプリでは、ユーザーが食事の写真をアップロードしたり、血圧や体重の記録データをPDF化して保存したりといったニーズも多く、ファイルストレージの容量確保は必須になります。
ノーコードツール内に基本容量が含まれている場合もありますが、ユーザー数やファイル量が増えると、追加料金が発生する仕組みです。
さらに、アプリを「●●health.jp」などの独自ドメインで公開する場合には、以下のようなインフラ関連の維持費が発生します:
- ドメイン取得・更新費(年1,000〜5,000円)
- SSL証明書(セキュリティ確保/年間3,000〜8,000円)
- DNS設定・運用サポート費用(数千円〜)
【目安】
インフラ関連のコスト全体で、年間1万〜3万円程度を見込んでおくと安心です。
3-3. 保守・運用のランニングコスト
アプリのリリース後には、バグ対応・アップデート・ユーザーサポートなど、細かく継続的な作業が発生します。これを外部パートナーに依頼する場合、月1〜5万円前後の費用がかかるのが一般的です。
特にヘルスケアアプリは、ユーザーの日常的な健康行動に密接に関わるため、アプリの安定性や信頼性に対する期待値が高く、「使えない時間=信頼の低下」にも直結します。
さらに、iOSやAndroidのOSアップデート対応や、新たに登場した法規制への対応(個人情報保護や医療関連ガイドライン)も随時発生します。
【実務の現場でよくあること】
- 「通知が届かない」「入力が保存されない」といった軽微な不具合
- 「新しい体重計に対応してほしい」などユーザーからの改善要望
- 「健康診断の記録をPDFで出したい」といった新しいニーズ
これらに柔軟に対応できる開発体制を確保しておくことが、運用初期のカギになります。
30秒でお問い合わせ!
- どのノーコードツールが最適なのか知りたい
- ノーコード開発の見積もりが欲しい
- Click・Larkについて詳しく知りたい
- ソウゾウのサービスについて知りたい
上記のような方はお気軽にお問い合わせください!
4. 開発費以外にかかる代表的な3つの費用
アプリの開発は、あくまでスタートラインにすぎません。特にヘルスケアアプリのように“生活習慣”や“健康管理”と密接に関わるサービスの場合、リリース後の「運用」「改善」「集客」「公開」といった運営フェーズの質が、アプリの価値を左右します。
ここでは、開発以外で発生しやすく、かつ見落とされやすい3つの代表的な費用項目を紹介します。これらを事前に想定することで、より現実的な事業計画と予算設計が可能になります。
4-1. 不具合対応・ユーザーフィードバック対応
アプリを公開すると、ユーザーからさまざまな反応や要望が寄せられます。特にヘルスケアアプリでは、「日々の体調記録が反映されない」「入力しづらい」「数値の単位が分かりづらい」などのユーザー体験に直結する声が多く挙がりがちです。
中には「血圧と脈拍の関係性をグラフで見たい」「睡眠記録を週単位で比較したい」といった前向きな改善希望もあります。こうした声に柔軟に対応できるかどうかが、継続率の分かれ道になります。
特にリリース直後は、想定外の不具合や改善要望が集中しやすいため、あらかじめ一定の開発リソースと改修予算(月数万円〜)を確保しておくのが現実的です。
4-2. マーケティング・プロモーション費用
どんなに機能が優れたヘルスケアアプリでも、認知されなければ使われません。特にターゲットが生活習慣改善を目指す一般ユーザーや医療従事者などに広がる場合、信頼性と魅力を伝えるマーケティング戦略が不可欠です。
代表的な施策としては:
- SNS広告やインフルエンサーを活用した生活者視点での導入訴求
- ヘルスケアブログや専門メディアとのタイアップ記事
- LP(ランディングページ)+SEO設計による検索流入の確保
- ストア評価やアプリ説明文を最適化するASO(App Store Optimization)
- 健康診断キャンペーンやクーポン配布による初期導入のハードル下げ
これらを実施するには月数万円〜数十万円の広告費用やコンテンツ制作費が必要となる場合もあるため、「どの施策に、いくら投資して、何を得るか」を定量的に設計し、KPI(例:1DLあたりのコストや継続率)で効果を検証していく必要があります。
4-3. ストアリリース費用(iOS/Android)
アプリを世に出すためには、iOS/Androidの公式ストアに公開する必要があります。これは一度きりの費用というよりは、毎年かかる維持コストと捉えるのが現実的です。
| ストア名 | 登録料・更新料 | アプリ内課金の手数料 |
|---|---|---|
| App Store(iOS) | 年間99ドル(約15,000円) | 課金額の15〜30% |
| Google Play(Android) | 初回25ドル(約3,750円) | 課金額の15〜30% |
さらに、課金型ヘルスケアサービス(例:プレミアムプランや有料機能)を導入する場合は、この手数料を差し引いた後でも利益が成り立つかどうかを、あらかじめ収支シミュレーションしておく必要があります。
また、医療系ジャンルのアプリは審査がやや厳しくなる傾向があるため、ガイドラインへの準拠や再提出対応の工数も見込んでおくと◎です。
5. 開発費に差が出る5つの要素
ヘルスケアアプリの開発費用は、「機能数 × 開発期間 × 人件費」といった単純な式で計算できるように見えますが、実際にはもっと複雑です。
たとえ同じようなコンセプトのアプリであっても、見積もりに大きな差が出る理由は、以下のような構造的な違いにあります。
5-1. 機能の数と構成
最も分かりやすい費用差の要因が、「搭載する機能の数」と「その構成の複雑さ」です。たとえば、以下のような機能を想定してみてください。
- 毎日の健康記録(日記、体温、体重)
- プッシュ通知での服薬・運動リマインド
- チャットボットによるアドバイス
- 行動習慣を可視化するウィークリーレポート
- ゲーミフィケーション要素(バッジ、スコア)
これらの機能を組み合わせれば組み合わせるほど、設計・実装・テストの工数は雪だるま式に増加します。
5-2. 健康情報の管理や医療連携に関わる特殊ロジック
レンタルアプリで言う「貸出管理・決済」にあたる部分が、ヘルスケアアプリの場合は「健康データ管理・医療連携」になります。たとえば、
- ウェアラブル端末(Apple Watch、Fitbitなど)とのリアルタイム連携
- 電子カルテや病院システムとのセキュアなAPI連携
- 病歴や診療記録に応じた機能制限やコンテンツ出し分け
- 保険との連動や医療費控除情報の自動出力
こうした高度な業務ロジックがあると、通常の健康記録アプリとは別次元の設計・開発スキルが求められます。データの正確性や扱い方に関する責任も重くなるため、コストにもその分反映されます。
5-3. セキュリティ・法令対応レベル
ヘルスケアアプリは個人情報の中でも最もセンシティブな「健康・医療情報」を扱うため、法的・倫理的な対応レベルが高くなります。たとえば、
- 通信のSSL暗号化
- ログイン時の二段階認証
- アクセス制御(医師だけが閲覧できる情報など)
- GDPRや日本の個人情報保護法への対応
- アプリ内の同意取得やプライバシーポリシー設計
特に、薬機法や医療機器プログラムの範囲に該当するか否かで、開発コストと必要な監査・認証の有無が大きく変わります。
セキュリティは“後付け”で対応すると倍以上のコストになるため、開発初期段階で要件を明確化しておくのが重要です。
5-4. デザイン・UI/UXの精度
健康に関わるサービスだからこそ、信頼感・安心感・直感的な操作性がUI/UXには求められます。たとえば、
- 高齢者ユーザーがメインなら大きなボタンと明快な配色
- 若年層向けならスタイリッシュなデザインとインタラクション
- 医師や看護師が使う場合は業務効率と視認性の最適化
こうしたターゲットに応じたUI設計やアニメーション処理、ナビゲーションの構成まで含めて丁寧に作り込むと、その分だけ工数と費用が増加します。
逆に、テンプレートベースで割り切ることで初期費用を抑える選択肢も可能です。どこにこだわり、どこを割り切るかが重要になります。
5-5. 要件定義の明確さと修正頻度
見落とされがちですが、開発費を押し上げる最大の原因が「開発中の仕様変更」です。
- 「やっぱりこの画面、もうちょっとこうしてほしい」
- 「医療監修が入って、この機能を追加する必要が出てきた」
- 「当初想定してなかったOS対応が必要になった」
こうした仕様の“後出しジャンケン”が増えると、再設計→再開発→再テストのループに突入し、費用が予想以上に膨らんでしまいます。
だからこそ、最初の企画段階で以下を固めておくことが費用を抑えるカギです:
- MVP(最小構成)の明確化
- 優先順位づけ
- 対象ユーザー像の明文化
しっかりと土台を固めた要件定義こそが、開発費を最小化し、開発スピードを最大化する鍵となります。
6. 費用を抑えるための賢いアプローチ3選
ここまで読んで、「やっぱりヘルスケアアプリの開発って高い…」と感じた方もいるかもしれません。
しかし、費用をかけるべきポイントと、削れるポイントの見極めさえできれば、コストパフォーマンスの高い開発は十分に可能です。
ここでは、実際に多くの医療・健康領域の成功事例でも採用されている、“賢いコスト最適化アプローチ”を3つ紹介します。
6-1. MVP思考で「段階的に機能追加」する
開発費を圧迫する最大の要因は、「最初から全部盛り」で作ろうとすること。
たとえば、
- ユーザーの健康記録
- 医師とのチャット相談
- 食事・睡眠・運動の自動分析
- AIによる健康スコア算出
…これらをすべて同時に実装しようとすれば、費用も時間も膨らみます。
まずは「健康記録だけ」「ウェアラブル連携だけ」などMVP(最小実行可能機能)に絞ってリリースし、ユーザーの反応やニーズに応じて、必要な機能を後から追加していく設計が現実的です。
この“段階的アプローチ”は、無駄な機能実装を防ぎ、早期リリース→早期フィードバックという健全なPDCAの実現にもつながります。
6-2. 実績のある開発会社に依頼する
「なるべく安く作りたい」という気持ちは自然ですが、費用だけで開発会社を選ぶのは危険です。
特にヘルスケア分野では、
- 医療法や個人情報保護法への理解
- 健康データの安全な取り扱い
- 医師や看護師との連携設計 といった、専門的な知見と経験が不可欠です。
実績のない開発会社に依頼すると、後からの手戻りやセキュリティ不備で想定外の費用や時間がかかるリスクがあります。
過去にヘルスケアアプリの開発経験があり、医療・健康に関する規制や設計に精通している開発パートナーを選ぶことで、最終的なコストと品質を大きく最適化できます。
6-3. 補助金・助成金制度を活用する
ヘルスケアアプリは、「地域医療のDX」や「予防医療の促進」といった政策分野と親和性が高いため、以下のような補助金や助成金の対象となるケースが多くあります。
- IT導入補助金(最大450万円支給)
- ヘルスケア産業創出支援事業(自治体・省庁主導)
- 小規模事業者持続化補助金(最大200万円)
- 介護・医療系スタートアップ支援助成 など
特に、ノーコード開発やSaaS連携を用いたサービスは採択率も高い傾向があります。
補助金は申請や報告が必要な分、手間はかかりますが、自己負担を最大80%近く削減できる可能性があるため、ぜひ検討する価値はあります。
※補助金の相談ができる開発会社もあるので、あわせて問い合わせてみるのがおすすめです。
7. まとめ|「つくる」より「育てる」視点で設計する
アプリ開発とは、単なる「ものづくり」ではなく、「事業づくり」です。どれだけ良い機能を備えていても、それが使われ続け、収益を生み、チームが持続的に運用できなければ意味がありません。
ノーコードの活用や補助金制度の併用によって、たしかに初期コストは抑えられます。しかし、それ以上に大切なのは、アプリが「使われ続ける構造」を持っているかどうかです。
そのためには、開発フェーズの前にこそ考えるべき問いがあります。
- 誰に、何を届けるのか?
- どう収益を生み、どう成長させていくのか?
- どのくらいの体制・コストで運用を回せるか?
こうした問いをもとに、MVP設計・ロードマップ策定・体制設計まで含めた「全体像の構想」が必要です。
最小の投資で最大の成果を出すためには、「作る技術」以上に「育てる視点」と「戦略設計力」が武器になります。
その準備こそが、あなたのアプリを“単なるプロダクト”から“持続可能な事業”へと進化させる土台になるのです。
ノーコード開発に関するご相談はソウゾウまで!
ソウゾウでは、数多くのノーコード開発実績より、お客様のプロジェクトの目的ごとに最適なノーコードツールのご提案〜設計〜デザイン〜実装〜リリース〜保守運用まで一貫してサポートさせていただいております。
・ノーコードを活用し、アプリ・システムをマルっと構築して欲しい
・アプリ/システムの土台の構築依頼とその後の運用の内製化(開発人材の内製化)までやってほしい
・ノーコード人材/開発人材/IT人材を内製化してほしい など
上記のようなご要望をお持ちの方は、下記よりお気軽にご相談ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
30秒でお問い合わせ!
- どのノーコードツールが最適なのか知りたい
- ノーコード開発の見積もりが欲しい
- Click・Larkについて詳しく知りたい
- ソウゾウのサービスについて知りたい
上記のような方はお気軽にお問い合わせください!